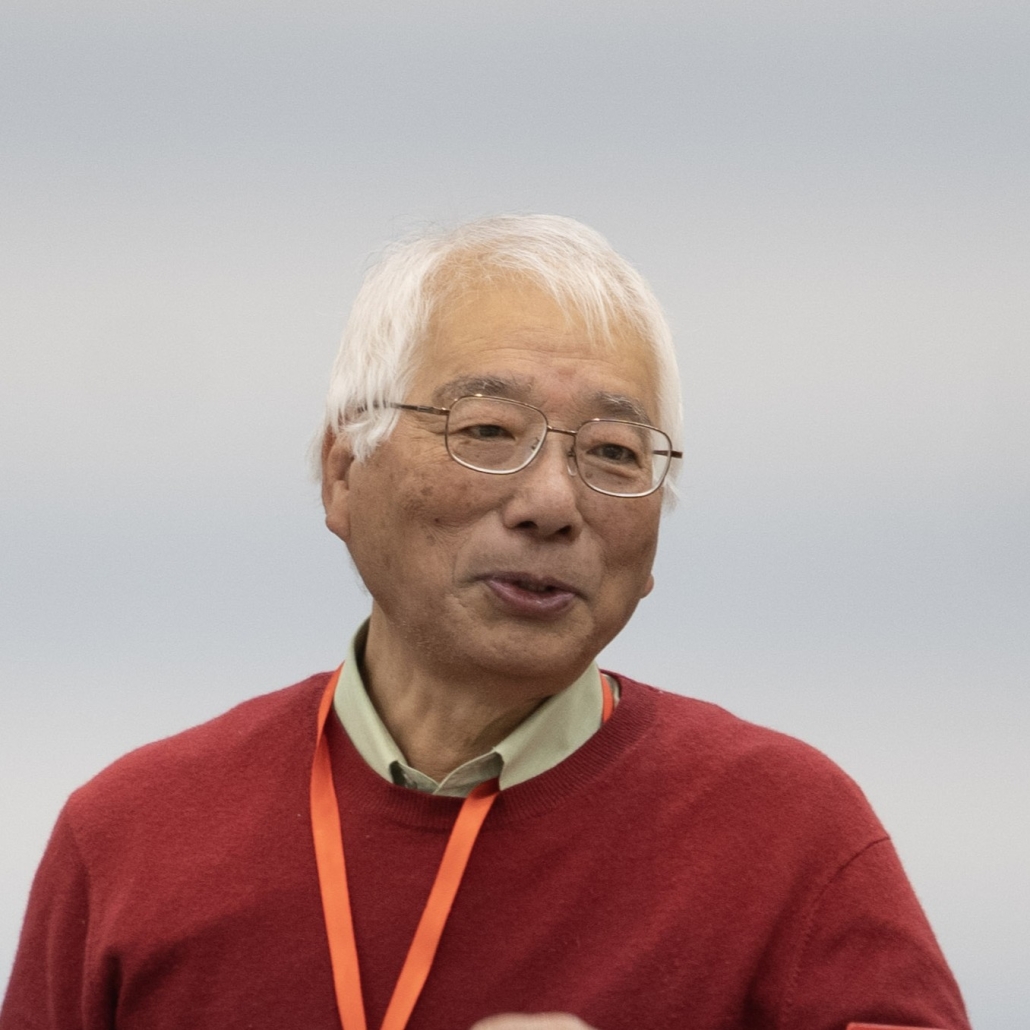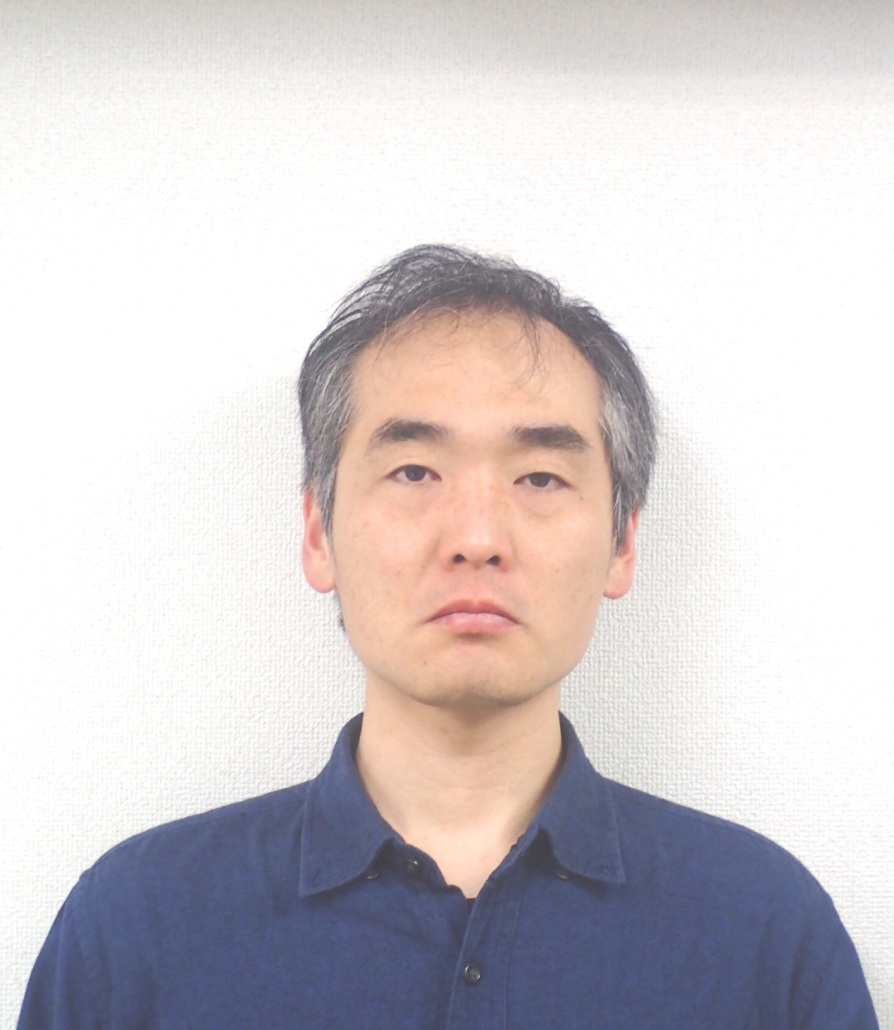キッズ・サイエンスカフェ
セッション1
2025年11月23日 10:00~11:30 2階中会議室前オープンスペース
花粉を運ぶマメコバチはリンゴがお好き?
花粉を運んでくれるハナバチの中には、ミツバチよりも小さくて、素早く花から花へと動き回るものがいます。
春先のリンゴ園などで活躍するマメコバチはその代表です。彼らは、筒状になった場所に巣をつくります。
リンゴ農家さんは、巣がつくられた筒をリンゴの花が咲く時期に用意して、受粉に役立てています。
このマメコバチはどんな姿でしょうか。また実際にはリンゴの花以外にはどんな植物を利用しているのでしょうか。
このサイエンスカフェでは、実物やスライドを見ながら、ミツバチと同じように役立っているマメコバチについて紹介していきます。
ハナバチの進化をたどる
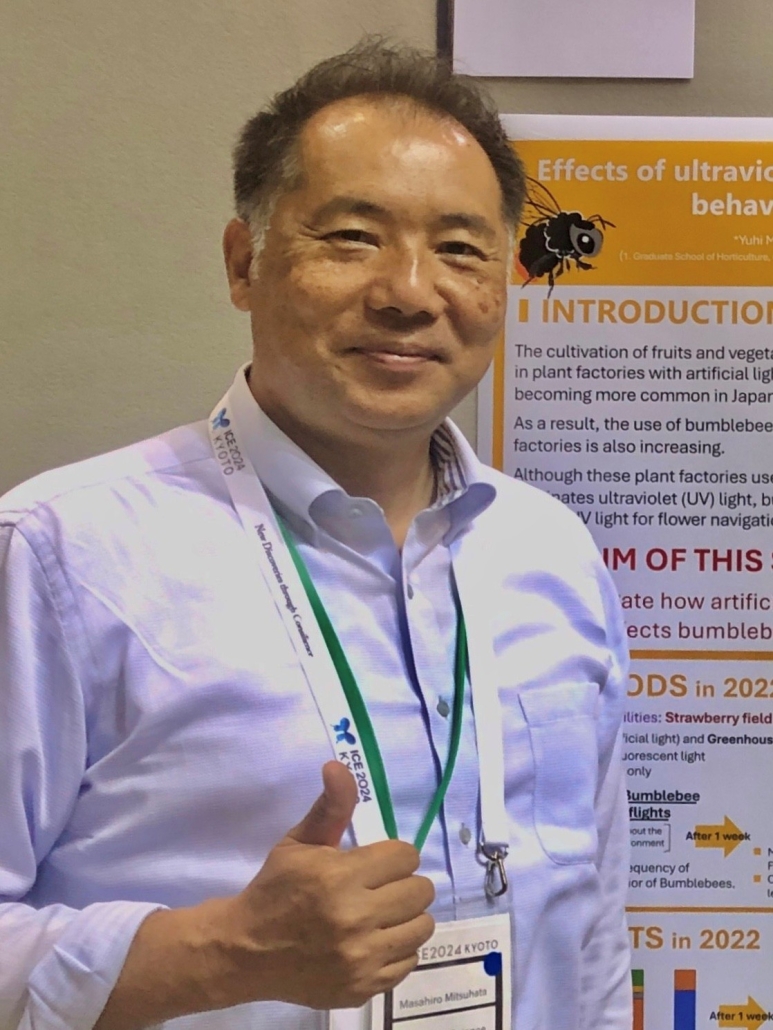
光畑雅宏 Masahiro Mitsuhata
千葉大学園芸学研究院 非常勤講師
ハナバチと植物の関係、ハナバチを農業に利用する研究をしています。
なぜ、ミツバチやハナバチは花粉や蜜を食料とするようになったのか?
ハチの祖先はそもそも何を食べ、どのように暮らしていたのか?
ミツバチに代表される大きな巣の中で集団で暮らし、幼虫を育て、蜜などを貯める社会性の生活様式は、実は非常にマイナーなもの。
多くのハチは単独で暮らし、巣づくりすらしないハチも多く存在します。
ミツバチはどのようにして、私たちが想像するハチの生活をするようになったのか?
ハナバチ以外のハバチ、寄生蜂、カリバチなどの生態も垣間見ながら、ハチの進化を紐解いてみましょう。
ミツバチの脳を見てみよう

宇賀神 篤 Atsuhi Ugajin
城西大学分子生理学研究室
ミツバチのすごい能力を遺伝子や脳の仕組みから研究しています。
昆虫は私たちとは見た目も大きさも違いますね。
しかし,そんな昆虫たちも私たちと同じように,仲間の居場所を見つけたり,食べ物のありかや危険な場所を学習したりと,頭(脳)を使って懸命に生きています。
中でもミツバチは,花の場所を覚えて仲間にダンスで伝えるという離れ業をやってのけます。
ミツバチの脳の中は一体どのようになっているのでしょうか?
今回は実際に脳を観察してみましょう!
そして,他の昆虫と比べてみると,ミツバチならではの特徴が見えてくるかもしれません。
セッション2
2025年11月23日 15:00~16:30 2階中会議室前オープンスペース
ニホンミツバチの不思議な世界とはちみつ
花を求めて飛び回るミツバチ。
気楽な生活?ではなく、命を奪う敵も多い過酷な世界。
そんなミツバチの世界を写真と映像で紹介します。
ハチミツについても、新鮮なハチミツと古蜜の違い、ハチミツから作る酢の話、日本最南端で南国フルーツのライチからとれるハチミツの味など紹介します。
試食も予定していますのでお楽しみに!
ハナバチのたどったみち
花を訪れ、花粉や蜜を集めて暮らすハチがいます。
そのハチは、ハナバチと呼ばれるグループで、よく知られているミツバチやマルハナバチも同じハナバチの仲間です。
彼らは、この地球上にいつ出現し、花と関わりながら多様化していったのでしょうか?
また、ハナバチの祖先は、どのようなハチだったのでしょうか?
このようなハナバチのたどってきた道(進化)について、最近の研究成果を踏まえ紹介するとともに、現生のハナバチがおかれている現状についても、紹介していきます。
ハチはごちそう-ラオスの蜂食文化を訪ねて

溝田浩二 Koji Mizota
宮城教育大学
ニホンミツバチやハリナシバチなどの研究で世界を飛び回っています。
ラオスは世界でもっとも昆虫食が盛んな国のひとつ。
スズメバチやミツバチの仲間は特に人気の高いごちそうです。
危険を承知のうえでハチを捕まえ、調理し、みんなでおいしくいただくーそんなラオスの人々の豊かな蜂食文化を紹介します。
皆さんのハチに対するイメージが”コワイ”から”オイシソウ”に変わるかも!?
![]()